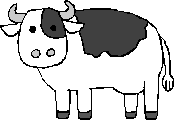
マーラーを聴く牛達
清里(山梨県)
山根貴以子 |
|
今からちょうど10年前の5月、友人と二人で清里高原に旅行したときのことです。
そのころ私達は、マーラーにかなり傾倒していた時期でしたので、この旅の目的を、大自然の懐でマーラーの牧歌風の「交響曲第四番」を聴き、マーラーの宇宙を体験したい、と考えていました。
二人は高校生の息子のラジカセを借り、小海線に乗り、風薫る甲斐小泉駅に降りました。
翌日は宿泊先の「泉郷」というところから高原を30分程登った所の、県 営の広大な牧場へ行きました。 営の広大な牧場へ行きました。
「関係者以外、立入禁止」という立札がありましたが、そこはオバさん二人、立札を無視して、「ここは格好のロケーション」とばかりに、さっそくボリュームを最大に上げてスイッチ・オンしました。
その日は曇りで、ときおり霧雨になったりして、絶好のお天気とはいえませんでしたが、二人はそこに横たわり、目をつぶって音楽を聴きはじめました。
第三楽章から終楽章に変わろうとするころ、"わさわさ"という音がしたので、人が近づいて来たのかなと、二人とも同時に目を開けました。
びっくり仰天しました。
細い針金のフェンスがあるとはいえ、私たちの目の先すぐのところ、1メートルあるかない近さで、ビクターの犬のように首を傾けた25頭(後で数えたのですが)の牛が、ボス牛らしい牛を先頭にしてピラミッド型に整列して音楽を聴いていたのです。
牛達は、私達がそれと気づかないほど、静かに集まって来ていたのです。
都会育ちの私達は、牛の生態を何も知らなかったので、ただただ驚いて25頭の牛に踏み潰されてしまうのではないか、という恐怖心で、とっさにラジカセのスイッチを切り、本気で、牛の気持ちを高ぶらせる様な赤いものがあったら大変と思って、回りを見廻りしました。
そしてラジカセが赤だったのに気づき、思わず上着で覆いました。 |
 |
音楽を切ると牛は三々五々、ゆっくりと草を食みながら元いた方へ帰って行きました。
この牧場は、去っていく牛の姿が豆粒ほどにしか見えない程、広大な草原でした。
しばらくして、冷静になってきた私達はもしかしたら牛も私達同様に、美しい音楽を楽しみたいのではないかと気づき、再度マーラーを流しました。すると牛達は帰って行ったそのままのリズムで、ノロノロと草を食みながら私たちに近寄ってきました。
そしてフェンスの向こう側でピラミッド型に整列して、首を傾けて聞いているのです。
耳にはオレンジ色や黄色の固体番号のイヤリングをつけていました。
私達はその愛らしさに、もう自分達の音楽鑑賞は二の次になってしまい、牛のことで頭がいっぱいになってしまいました。 |
 |
そこで、曲を変えたらどういう反応をするのか、面白がった二人は、その日持参したカセット・テープの中からアトランダムに、ドヴォルザーク「チェロソナタ」、バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ」、ラヴェル「ボレロ」などを聴かせました。
統一のないレパートリーでしたが、どの曲にも全頭とも、お行儀よく整列をしたまま動こうとせず、音楽を楽しんでいるようでした。
そろそろ私達も帰る時間となり、音楽をかけながら牧場を後にしたのですが、25頭の牛は行儀よくピラミッド型に整列したままで私達を見送ってくれました。
牛も、私達人間同様に音楽を聴く感受性を持っていることを知り、言葉では言い表せないほどの感動を受けました。
以前、新聞に、「ある牧場では牛に音楽を聴かせて記憶させ、夕方には人を使わず牛を牛舎に集めることをしている」という記事を読んだことがあります。条件反射を利用するだけに音楽を聴かせることは、経営的には重要でしょうが、彼ら(食肉牛)は人間に食べられる目的で生かされているのです。
せめて、そういう人間の側からの目的だけのためではなく、彼ら自身のためにも良い音楽を聴かせてあげたいと、切に思いました。
この日は、全く思いがけなく牛達に素晴らしいプレゼントができた幸福な一日になりましたが、この旅の目的が達成されたばかりではなく、私達にとっても魂の奥底にあるSomethingを喚起してくれた忘れられない旅となりました。(2003年 早春) |
= 山根貴以子 =
大手商社勤務を経て現在ギャラリーKIKIのオーナー。
夫・治仁氏とともにベイタウンシニアクラブに入り、住民として地域文化に貢献。その他、幅広い活動をする。ベイタウン在住。
●ギャラリーKIKI ホームページ | |

